
こんな甘ったるい声で喘がれては、武ならずとも男なら誰だって至福の桃源郷と表現したくなるに違いなかった。 弾力良し、温かさ良し。 景観? 見えない。黒く塗り潰されたかのように何も見えないのだがむしろそれこそが絶景かな、絶景かな。 良いコト尽くしのように、思えなくもない。 思えなくもないが…… 「……ぐむぉー」 パプアニューギニアの奥地、秘境に住まう珍生物が如き唸りをあげて、武は抗議した。 その抗議に対する反応たるや―― 「んっ、く……っ」 ――これだった。 先程とは反対側。 もう一つ、別の喘ぎが頭を蕩かした。 |

果たして何が最悪なのか。 現世の楽園をして武に最悪と言わしめる要因とは、 「……あっ♥」 「……はぅっ」 武の頭を挟んで左右から。 同時に聞こえてくる甘美なステレオヴォイスが、男の色んな純情を悩ませるのだ。 楽園であるのと同時に、これは地獄の拷問にも等しかった。 当たり前だ。 我慢は身体の毒、禁欲は何も生みだしやしない。 精神的にも肉体的にも、よろしくないのは明白だった。 本当に、とてもよろしくない。 「……もんぐぅおー」 エロマンガ島近海に住まう伝説の怪魚の名前にも似ているかも知れないし似ていないかも知れない唸りをあげて、武はなんだかもう啜り泣きたくなってきた。 男の子なのに。 男の子だから。 「……は、んっ……はぁ。……どうしたのだ、タケル?」 「ふぁっ♥ ……はぅう。……どうかなさいましたか、武様?」 ムニュリ、と。 視界が歪んだ。 |
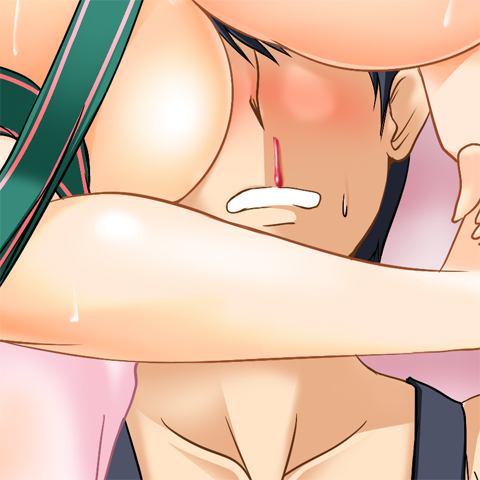
「……いや、そのだね、キミ達」 「うん?」 「はい?」 無邪気な声だ。 なんともまぁ、無垢な声だ。 しかし騙されてはいけない。これは悪魔の囁きなのだ。武を堕落させ、欲望渦巻く邪悪暗黒魔界に引きずり込もうと画策する可愛らしい双子の悪魔ッ子の―― ――ムニュル。 「ムニエル!」 武は叫んだ。 悲しい、魂の咆哮だった。 未来の見えない咆哮だった。 「? タケル、そなた、ムニエルが食べたいのか?」 「まぁ。では料理長にはそのように……」 悪魔は際限なく凶悪だった。 |

「ところで武様、ムニエルと申されましても」 ムニムニ。 「お魚は、何にいたしましょう?」 ムニェル、ムニェル。 なんだかありえない効果音が武の頭を埋め尽くす。今や、脳内は味噌バターどころか怪魚モングゥオーのムニエルでおっぱ――いっぱいだった。 「ふむ。タケルは鯖の味噌煮が好きだし」 ムニエール、ムニエ〜〜〜〜ル。 「魚は和食党なのかと思っていたが、洋食も好きなのだな」 和食とか洋食とかよりただ単にムニエルだった。 もう、なんだろう。 「……ぐぁ」 思いっきり、ムニエルしたかった。 今の、この、冥夜と悠陽にサンドイッチされた状態で。 |

「……なぁ」 力無く、武は口を開いた。 「うん?」 「はい?」 やっぱり邪気のない、純真な声だ。 けれど悪魔は天使の姿を借りてやって来るのだ。武は騙されてなるものかと頭を振った。 だが、オッパイサンドイッチされた状態でその中の具がグリグリ動いたら、いったいどうなるだろう。 答えは簡単。 「ふぁああああっ!?」 「はぁあああんっ!?」 悩ましいステレオが大音量で武の脳味噌をムニエル。 「――――――――――ッッ!!」 声にならない悲鳴をあげて、昇天しそうになるのを懸命に、必死に地上にしがみつく。 まだ死ぬわけにはいかない。 まだ死にたくはない。 でももしかするとここは既にあの世なのではないだろうかと懊悩しつつ、武は震える唇でようやく続きを紡いだ。 「……二人とも、なんで……どうしてこんなコトしてんだ?」 力を、生命を尽くした質問だった。 なのに答えは簡単だった。 「……う、うん。その……プ、プレゼントだ」 「ええ。クリスマスのプレゼント、でございます♥」 言うなり、悠陽がさらに身体を……有り体に言えばオッパイをググイグイッと密着させてきた。 「ぬおぉおおっ!?」 「あ、姉上!?」 |

「まぁ、冥夜。そのように睨まないでください」 「だ、誰も睨んでなど……」 頼むからオッパイで人の頭をキモチよーくこねくり回しながら姉妹喧嘩はやめて欲しいなぁと思うのだが、今の武に反論に消費出来るエネルギーなど残されていなかった。 なんというスーパーピンチ。 そんな名前のロボットを前世で殴り壊したことがあったような気がしなくもなかったが、武は質疑を続けることにした。 「……プレゼントって。お、お前ら、誰に入れ知恵された?」 「ん? 月詠だが」 「真耶さんと真那さんです」 訊くまでもなかった。 ホホホッと笑う真那と、相変わらず無表情な真耶の顔が一瞬頭を過ぎり、すぐ消えた。 消えざるをえなかった。 だって。 「あ、姉上! ですからタケルにくっつきすぎです!」 「あんっ!?」 |

今度は冥夜の側に頭をハグハグ……もとい引っ張られ、武は素晴らしき肉地獄に埋没した。 ヤバイ。 溺れる(呼吸的な意味で)。 「むぐっ! むごぉおおっ」 「冥夜、それはいくらなんでも酷すぎはしませんか? 独占禁止法くらい、存じておりましょうに」 「あ、姉上こそ! ……た、確かに女としての魅力では私は姉上に劣っているやも知れませんが、この勝負、一歩たりとも退くわけにはまいりません……!」 武の頭を左右からオッパイでムニンフニョングニュリぷるんっと挟み潰しながら、姉妹は互いに退けぬ天王山とばかりに、さらに強く情熱的に、合計四つの天王山を愛する男に押しつけた。 |

……なんか、もう、いっそこのまま欲望に負けてもいいんじゃないか、と。 自分よく頑張りましたよなんて言い訳しつつ、武はヤケクソだとばかりに二人の乳房に手を伸ばそうとした。 明日の朝、純夏が目にして何を言うか。 まず間違いなく成層圏を突破して月にクレーター穿つくらいぶっ飛ばされるんだろうなぁと的中率100%の予知をしつつも、ここまできたなら止められる道理が無い。 ――えぇい、ままよ! ―― 姉妹丼、なんて言葉がどこからともなく浮かび、海の泡のように儚く、消えた。 シマイドンとカタカナで書くと怪獣のようだ。 そして今、自分は怪獣に、獣になるのだ。 肉欲獣上等! とばかりに理性の鎖を引き千切った武は荒ぶる雄の本能のままに二人の乳を揉みしだこうとし、 「し、ししし白銀ぇええ! 寒い、寒いわ!!」 「ししししろろろがねねくぅ〜〜〜んッ! メ、メメリーククリリマスス――……って」 突如、扉を蹴破って現れたサンタとトナカイいえどう見てもよく知っている女教師二人それどころか一人は間違いなく自分の担任です本当にありがとうございましたに、目を丸くした。 「あんたぁ! 人がこんな格好でクソ寒い思いしてんのに姉妹丼たぁイイ度胸してるわねぇ!?」 「不潔よ! 不純異性交遊なんてダメよ三人とも! こういうことはもっと大人になって責任をとれるようになってから……」 片方は明らかに逆ギレだったし、もう片方も赤鼻つけて泣きながら説教されても、武と冥夜、悠陽としてはそんな事よりどうして女教師二人が深夜男子生徒の部屋に痴女みたいな格好で押し掛けてきたのかをまず事情聴取したかった。 特に姉妹にしてみれば、教師であれど相手は女性だ。 「白銀君!」 「ひゃ、ひゃいっ!?」 「そもそもこういうことは、男の子であるあなたがもっと気をつけないとダメでしょう!? ……べ、別に男女交際そのものを否定はしないのよ? でもね、やっぱり一度に二人を相手にするとかそういうのはイケナイことだし……わ、わかるでしょ!?」 顔を真っ赤にして武を叱りつけるまりもを見つめる姉妹の目は、複雑だった。恋敵に溢れまくっている現状、生徒と教師にそんな関係、感情はありえないなんて悠長なことは言っていられない。夕呼はまだしも、まりもと武が一般的な担任と生徒よりも仲がいいのは悠陽にせよ冥夜にせよ、察していた。 「……あの、神宮司教諭」 「え? ……あっ」 悠陽がどうして自分の名を呼んだのか、まりもは女の直感としか呼びようのないもので瞬時に悟った。我ながら嫌な言い方でも、踏んだ場数が違う。勝ち戦負け戦は別として、女としての経験は彼女達よりも余程に豊富なのだ。 だから、わかる。 悠陽と冥夜が抱いているであろう懸念が。 「不躾ではありますが、どうしても確認しておきたいことがあるのですが、よろしいでしょうか?」 「な、なに、かしら?」 大人の余裕で返すべきなのだろうと、そう考えながらもまりもの頭の中には先程の夕呼の言葉が喧しく反響していた。 ――武が、最後のチャンス。 いや、最後かどうかはこの際どうでもいいのだ。そもそも、自分は武をチャンスとして――要するに、一人の男として、捉えているのかどうか。 「神宮司教諭は、……その」 悠陽も、相手が担任教師であるまりもとあっては流石に言い倦ねていた。その時間が、双方共に辛かった。 錯綜する混乱と思惑はやがて沈黙を生んだ。 「……う、ぁー……」 そんな中で呻いたのは、武だった。 まずは落ち着くべきだろう、と。誰ともなく皆が互いに牽制し合う雰囲気から生まれた、この場の凄まじい気まずさから武は逃げ出したくてたまらなかった。 が、事態は常に流動的で、運命は彼に停滞することも安易に逃避することも許さない。 「タケルちゃーん! 夜中になぁに大騒ぎしてんのぉ……――って……」 一番ヤバイ奴が来た。 来てしまった。 もう、言い訳する気力すら無い。 それでも一応、武は純夏に説明を試みようとした。 「あ、あのだな、純夏!?」 「却下」 即答だった。 純夏の全身から放たれるオーラがまるで放電現象でも起こしているかのようにバチバチと火花を散らし、ユラリ、と無想が転生し流れるようにして、動いたと認識した瞬間には……その拳は、放たれていた。 「こぉおおおおおおおのド畜生がぁああああああああああああああああああああああああああッッ!!」 「シュハキマセリィイイイイイイイイイイイイイイイイッッ!?」 聖なる夜に、星が、流れた。
「まりも、あんた、助かったーなんて思ってるでしょ」 「えっ?」 帰りの車中で、正面を見据えている夕呼は憮然としているような、それでいて可笑しさを堪えているような、なんとも判断しづらい表情で助手席のまりもにそう投げかけた。 「……〜」 何か言い返そうとして、まりもはやめた。どうせ口で勝てる相手ではないのだ。それに、否定の言葉は、きっと嘘になってしまうから。 本当のことは口に出来なくとも、クリスマスくらい、せめて嘘はつかずにいたかった。 「……まっ、いいんだけどね」 小さく肩を揺らし、夕呼はアクセルを踏み込んだ。 悠陽と冥夜は、屋敷の屋根にのぼり空を見ていた。 「もう、日付が変わった頃でしょうか」 「そうですね。姉上、そろそろ戻らないと、風邪をひきます」 姉の身を労る言葉を述べつつも、二人とも並ならぬ肉体的な鍛練を経てきている身だ。この程度の寒さで音をあげる身体ではない。 「……来年は」 「……はい」 「来年の12月24日と25日は、どのように過ごしているのでしょうね」 悠陽の呟きが、白く煙る吐息とともに夜の空に溶け消えていくのを見送り、冥夜は目を細めた。 満天の星空が、今にも落ちてきそうだった。 なのに武は、いつまでも落ちては来なかった。 「……」 呟きが溶けて消えてしまわないよう、冥夜は唇を愛しい男の名に動かすだけにして、音を呑み込んだ。 明日の夕飯はムニエルにするよう真那に言付けておこう。 冥夜は、そんなことを考えていた。 |
| 〜END〜 |