
――笑われていた。 「はっはっは! ほほ、ひーひひひ! 最高、まりも、あんた本当にサイコーよ!」 神宮司まりもは、笑われていた。 学生時代からの無二の親友(のはずである)香月夕呼から、ズビシッと指差され、爆笑されていた。 「ちょ、なんでそんなに笑うのよぉ!?」 「……あら、異な事を言うわね」 ピタリ、と笑うのをやめた夕呼が、身も凍るような怜悧な眼差しを向けてきたことにまりもは思わず震えていた。背筋をつららで撫でられたかのようであった。 「笑っているのはあんたのためなのよぉ? まりも、考えてもみなさい。その格好に、こんな冷静で落ち着き払った視線を周囲から向けられて、あんた生きていけるの?」 「うっ」 夕呼の言う通りであった。 無理だ。とてもではないが、生きていく自信はない。そうなったら肉体よりも先に魂が、精神が死に絶えてしまう。年末の有明の方がまだマシというものだ。 だが、まりもにだって抗弁したい事はある。 「そ、そもそもこんな格好をさせたのはあなたでしょ!?」 |

そうなのである。 自分が今爆笑されていた格好は、他ならぬ夕呼に着せられた衣装であって、彼女がそれを見て腹を抱えて笑うというのはまったく不条理極まりない。 が、そんな親友からの抗弁を、夕呼は今度は鼻で笑った。 まさに嘲笑である。 「今さら何を言ってるのよ。賭で負けたら何でも言うことを聞く、って言ったのはあんたでしょ? それこそ、いつも通りに」 再び「うっ」と言葉に詰まり、まりもは後退った。 「それに今回はあんたをからかっていぢめ倒すのが目的じゃないのよ? 協力してあげるって言ってんじゃない。だからあたしもこうして一緒にコスプレしてあげてるんだから」 そう言って、その場でヒラリと手を回して見せた。 |

「……私だってまだそっちの衣装の方が良かったわよぅ〜」 恥ずかしそうに身体を押さえ、まりもは身悶えた。と言うより、寒いのである。車内でもこの寒さ、外に出たら一分と経たずに死んでしまうのではなかろうか。 窓から外を見ると、雪がしんしんと降っていた。 ホワイトクリスマス……なのに、感動が湧いてこない。 |

「まっ。もう少しの辛抱よ。そうすれば、孤独な寂しいシングルベルともおさらば、年下の恋人もゲット出来てあたしに猛烈に感謝したくなるわ」 「シ、シングルなのはあなたもでしょ!?」 精一杯の反抗も、相手が夕呼では儚いものである。 「あたしは好きであんたにつき合ってあげてるんだから、いいのよ。呼べば飛んでくる男くらい、いるしね」 事実であった。 非常識の塊、破天荒を地でいくようなマッドサイエンティストでありながら、夕呼の美貌はまるで真夏の誘蛾灯のように男共を惹き寄せる。彼女が一声かければ、たとえ遊ばれているのだと理解していようとも一抹一縷の哀れな期待、悲しい純情を奮わせてホイホイやって来てしまう男の数は、両の手に余るであろう。 「……はぁ」 改めて夕呼を頭から爪先まで眺め、まりもは嘆息した。 |

「なによ、その溜息は」 「……相変わらずスゴイ身体ねぇ、って」 「なに言ってんのよ。あんただって充分凄いわよ。凄くないのは男の扱い方だけで」 ゴイーンっと頭の上に重りを落とされたような気がしてまりもは俯いた。 「あぅ〜〜〜……」 「ほら、泣いてないでその立派なカラダでとっとと白銀をゲットしに行くわよ!」 そう言って車のドアを開けようとする夕呼を、まりもは血相を変えて引き止めた。 |
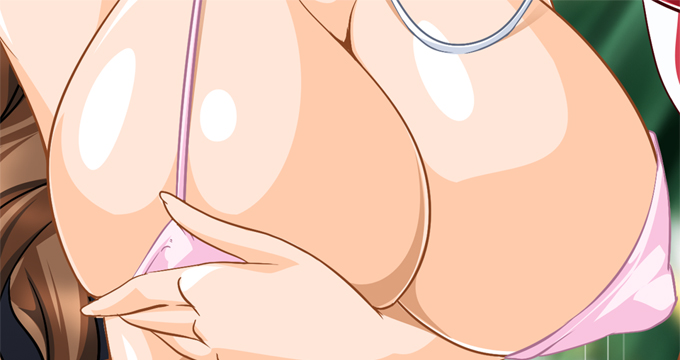
「だ、だだだだ、だから! わ、私は別に白銀君のコトは……その、あくまで教師と教え子として……」 「……まったく」 尻窄みになっていく親友の言葉に舌打ちし、夕呼は引き止める手を強引に振り解いた。 「あんたねぇ……この期に及んでそんなんだから万年男日照りのままなのよ! いい? まりも。白銀はねぇ、あんたに残された最後のチャンスなんだと知りなさい」 「ッ!?」 最後のチャンスという言葉がやたら鋭く胸に突き刺さり、まりもは絶句した。夕呼の言葉にはある種の魔力じみた説得力や強制力がある。長年の付き合いからそれらを身をもって知り、意識しているまりもであっても抗いがたい何かが、今の夕呼の言葉の中にはあった。 「ほらっ、行くわよ!」 「キャッ!」 先に車外に出た夕呼に助手席のドアを強引に開けられ、無理矢理に引っ張り出される形でまりもも外に出た。 |

サンタとトナカイ。 二人のコスチュームは、一応、クリスマスに則ったそれであった。それではあったのだが……まず、極悪に布地が少ない。ぶっちゃけてしまえば、これは最早コスプレどころの話ではなく痴女である。まりもでなくともこんな格好で男の、しかも年下、どころか教え子の家に押し掛けろと言われれば躊躇して当然であった。 下手をすれば、警察沙汰だ。白銀家と御剣家、鑑家以外に周囲に民家がゼロだから良かったものの、もし普通の住宅街のままであったなら二人は今頃間違いなく通報されていたであろう。 しかし現在、何よりも深刻だったのは―― 「さ、寒いぃいいいいいッ!!」 「……これはちょっと、寒すぎるわねぇ。は、早く白銀の家に入れてもらいましょ」 流石の夕呼も雪が降りしきる中に水着も同然の露出度ではたまらないらしく、震えながらまりもの手綱を引いた。 が、やはり踏ん切りがつかないのかまりもトナカイは震えながらサンタ……いや、まりも的にはサタンか。ともあれ、夕呼に儚く抵抗を続けていた。 「ちょ、ちょっとまりも、あ、あんたこのままじゃ凍え死ぬわよ?」 「で、でも、でも……あ〜〜〜〜う〜〜〜〜〜……」 凍え死にたくなければ車に戻るという選択肢もあるのだが、流石の超天才もあまりの寒さに思考が麻痺しかけていたため一刻も速く白銀家にお邪魔することしか考えが回らない。 「あー、もう仕方ないわねぇ! じゃあほら、コレつけてればアンタだってバレやしないわよ!」 「むきゅうっ!?」 いきなり鼻に何かをかぶせられ、まりもは目を白黒させた。 「ほ、ほら、は、はやくしないと……て、手がかじかんで……」 「ま、待ってぇ……こ、これ、鼻に何を……いぃい!?」 いったい何を鼻にかぶせられたのか、確認しようと車のサイドミラーに目を向けたまりもは素っ頓狂な悲鳴をあげ、次いで涙を溢れさせた。 「こ、こんなので正体隠せるわけが――」 「ほらっ、い、いい行くわよ!?」 |

「ひぃ〜〜〜〜〜ん」 鼻に赤鼻をかぶせられ、もう殺してとばかりに涙を滂沱させるまりもは、ドナドナの子牛もさながら力無く夕呼に引きずられていった。 |
| 〜To be continued〜 |